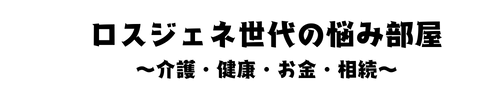介護者の現状とは?
介護者とは、高齢者や障がいを持つ方の世話をする人のことを指し、家庭内での介護を担う家族や、介護職として働く専門職の人々が含まれます。
現在、日本では高齢化が進み、介護の需要が急増しています。その一方で、介護を行う人々が抱える負担や悩みも深刻化しています。
本ブログでは、介護者の実態について、最新のデータをもとに大枠を解説します。
介護者が直面する主な負担
介護者にとって、日常的な介護作業は大きな身体的負担となります。特に、食事の準備、入浴の補助、排泄の介助といった作業は、介護者の体力を奪います。
厚生労働省のデータによると、介護者の約70%が身体的な疲労を感じていると報告されています。特に、介護者が高齢である場合、その負担はさらに増大し、介護者自身の健康にも影響を及ぼします。
身体的負担は、長時間にわたる介護によるもので、介護者の睡眠不足や体調不良につながることもあります。これが続くと、介護者自身が健康を害し、介護を続けることが困難になるケースもあります。
こうした状況を防ぐために、定期的な休息や他の家族や地域のサポートが必要です。
精神的ストレスの増加
介護は身体的な負担だけでなく、精神的なストレスも伴います。
介護者は、自分の生活を犠牲にして介護を行うことが多く、その結果、孤立感や無力感を感じることが少なくありません。特に、認知症の家族を介護する場合、コミュニケーションの困難さや、予測不能な行動への対応が大きなストレスとなります。
調査によると、介護者の約60%が精神的なストレスを感じており、うつ病や不安障害を発症するリスクが高いことが分かっています。
このような精神的ストレスは、介護者が長期間にわたって介護を続けることを困難にし、最悪の場合、介護離職に繋がることもあります。
介護による経済的な影響
介護は経済的な負担も大きく、家計に直接的な影響を与えます。厚生労働省のデータによると、介護にかかる平均費用は月額約7万円です。この費用には、介護用品、医療費、デイサービスの利用料などが含まれており、これに加えて、介護施設を利用する場合はさらに費用が増大します。
さらに、介護のために仕事を辞めざるを得ない「介護離職」も深刻な問題です。
介護離職者の経済的な影響は非常に大きく、家計が一人分の収入に頼ることになり、将来の生活への不安が増大します。また、介護離職後に再就職することが難しい場合も多く、長期的な経済的リスクが伴います。
深刻な介護離職:1年間に約7.3万人が介護等を理由に離職
厚生労働省の雇用動向調査によると、2022年に離職した人は約765.7万人、そのうち個人的理由で離職した人は約563.0万人でした。そして、個人的理由で離職した人のうち「介護・看護」を離職理由とする人は約7.3万人です。
男性は約2.6万人、女性は約4.7万人と女性のほうが多くなっています。
性・年代別に「介護・看護離職」の割合をみると、男性・女性ともに「55歳~59歳」で最も高くなっています。
社会的孤立とサポート不足
多くの介護者は、介護に追われる日々の中で自身の時間がほとんど持てなくなり、社会的に孤立してしまいます。特に、介護に専念するために友人や趣味から離れてしまうことが多く、孤独感が増大します。介護者の約50%が「相談できる相手がいない」と感じており、精神的な負担が蓄積されやすい状況です。
また、介護者支援制度や地域のサポートが不十分であることも課題です。
多くの介護者が、行政や地域社会からの支援を受けたいと考えていますが、手続きの複雑さや情報不足が利用を難しくしているケースもあります。このような状況では、介護者が支援を求めること自体がストレスとなる可能性があります。
介護者支援の必要性と今後の課題
介護者の負担を軽減するためには、政府や地域社会によるサポートが不可欠です。
介護休業制度や介護者向けの相談窓口の充実、地域でのサポート体制の強化が求められています。特に、地域コミュニティを活用した「レスパイトケア」(介護者が一時的に介護を離れ、休息を取ることができるサービス)などの取り組みが有効です。
さらに、介護者が安心して介護を続けられるよう、情報提供の充実と、手続きの簡略化が必要です。これにより、必要な支援をスムーズに受けられるようになり、介護者の負担を軽減できるでしょう。
まとめ:介護者の負担軽減に向けた取り組み
介護者が直面する負担は、身体的、精神的、経済的な面で多岐にわたります。
そのため、介護者が安心して介護に専念できるような環境づくりが必要です。
情報の提供やサポート体制の強化を通じて、介護者が孤立せず、適切な支援を受けられる社会を目指すことが重要です。
今後も、介護者の声に耳を傾け、直面している問題を共有し、より良い支援策を講じることが求められます。